救急救命士は消防に入ってから取るべきか?消防に入る前に取るべきか?
- いまおか先生
- 2025年9月3日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年9月4日
⚪︎この記事で学べること
・救急救命士とは?
・入庁前に取得するメリット・デメリット
・入庁後に取得するメリット・デメリット
・現場で感じる両者の違い
・あなたにとって、どっちが良い?
・あなたにとっての最適解を見つける
消防に関連する資格として代表的なのが「救急救命士」。ただ、その資格を取得する方法やタイミングは様々です。
今回は、救急救命士の資格についてしっかり学び、「自分にとっての正解」を見つけていきましょう。
僕は、東京消防庁OBであり、地方消防での勤務経験がある今岡です!現在は、消防士を目指す人に向けた採用試験塾「FFA」を運営しています!
⚪︎目次
⚪︎はじめに - 今のあなたの選択が10年後を決める

「救急救命士の資格、いつ取ればいいんですか?」
これは、消防士を目指す学生や転職を考える社会人から最も多く受ける質問の一つです。そして、この質問に対する答えは、あなたの消防人生を大きく左右する可能性があります。
僕は東京消防庁で2年間、地方消防で4年間勤務し、地方消防では主に救急隊として働いた経験があります。6年間の経験の中で、様々な救急隊員、救急救命士の方をこの目で見てきました。
この記事では、両方のパターンのメリット・デメリットを実体験に基づいて詳しく解説し、あなたにとって最適な選択肢を見つけるお手伝いをしたいと思います。単なる理想論ではなく、現場の生の声をお届けします。
⚪︎救急救命士の資格の基礎知識
・救急救命士とは何か
救急救命士は、病院外での救急医療において高度な応急処置を行える国家資格のことです。一般的な応急手当に加え、静脈路確保、薬剤投与、気管挿管など、医師の指示のもとで生命に直結する医療行為を行うことができます。
消防の救急現場において、救急救命士の存在は文字通り「命を救う最後の砦」です。心肺停止患者の蘇生率向上、重篤患者の病院前治療など、その専門性は年々重要度を増しています。
・資格取得の2つのルート
現在、救急救命士資格を取得するルートは大きく分けて2つあります:
1. 学校ルート(入庁前取得)
- 救急救命士の資格が取得できる専門学校(2〜3年制)で学習
- 救急救命士の資格が取得できる大学(4年生)
- 卒業する年の3月に国家試験を受験
2. 消防職員養成ルート(入庁後取得)
- 救急隊として5年以上もしくは2000時間の勤務
- その後、救急救命士の養成所で約6ヶ月研修
- 修了後に国家試験を受験
どちらのルートも最終的には同じ国家資格ですが、そこに至るプロセスと、その後のキャリアに大きな違いが生まれます。
⚪︎入庁前に取得するメリット・デメリット
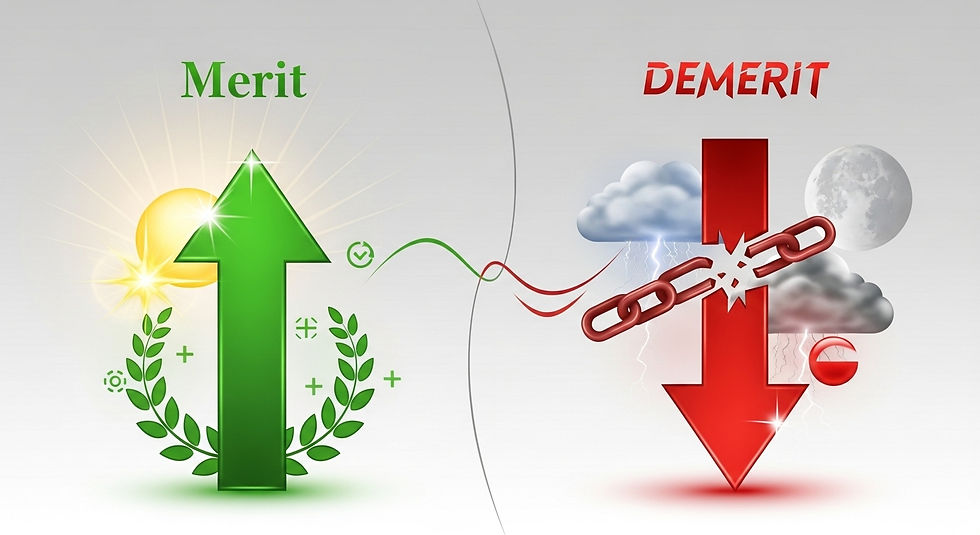
メリット1:即戦力としてのスタート
「新人なのに、ベテランと同じ医療行為ができる」
これが入庁前に資格を取得した者の最大のアドバンテージです。通常、新人消防士が救急救命士資格を取得するまでには5年程度かかりますが、入庁時点で既に高度な救急医療知識と技術を持っていることは、現場での大きな武器になります。
メリット2:専門的学習への集中
各種学校では救急医療に特化した濃密な学習ができます。消防業務の合間に勉強する入庁後取得とは異なり、2〜4年間を救急医療の習得に専念できるため、より深い理解と確実な技術習得が可能です。また、時間的な余裕も生まれます。
解剖生理学、外傷救急医学 、病態生理学など、医学的基盤をしっかりと固めてから現場に出ることで、応用力の高い救急救命士になることができます。
メリット3:採用試験でのアドバンテージ
消防本部の中には、救急救命士資格保有者を対象とした採用枠が設けられていることがあります。一般採用と比較して競争倍率が低く、採用される可能性が高くなります。
また、面接でも「救急医療への強い志向性」をアピールできるため、採用担当者に良い印象を与えることが多いです。
デメリット1:現場経験不足による戸惑い
医学的知識があっても、消防現場での実践は別物です。実際、救急救命士を持った筆者の同期は、「教科書通りの患者はいない」という現実に最初は戸惑っていました。
狭いアパートの階段での搬送、家族の動揺、現場の混乱、隊長独自の考えなどの要素が加わると、学校で学んだ通りにはいかないことが多々あります。
デメリット2:消防業務全般の理解不足
消防士の業務は救急だけではありません。消火、救助、予防業務など幅広い分野があり、それぞれが相互に関連しています。
入庁前取得者の中には、「救急以外はやりたくない」という考えの人もいますが、これは消防組織においてはマイナス要素になることがあります。チームワークを重視する消防の世界で、専門分野にこだわりすぎると孤立する危険があります。また、小規模の消防組織であれば人員の関係から、資格取得者であっても救急以外の業務を兼務することはよくあることです。
デメリット3:経済的負担
各種学校の学費は決して安くありません。2〜3年間で200〜400万円、大学だと650万円程度の費用がかかることが一般的です。また、この間はアルバイト程度の収入しかないため、経済的な負担は相当なものになります。
⚪︎入庁後に取得するメリット・デメリット

メリット1:豊富な現場経験をベースにした学習
「なぜこの処置が必要なのか」を現場経験を通じて理解してから学習するため、知識の定着率が非常に高くなります。
実際、入庁後に資格を取得した先輩によると「あの時の患者さんの状態はこういうことだったのか、という気づきの連続だった」とのことでした。現場経験があるからこそ、教科書の内容が立体的に理解できるのです。
メリット2:消防業務全体の理解に基づく専門性
消火、救助、予防業務をすべて経験してから救急救命士になることで、「消防業務全体の中での救急医療の位置づけ」を正確に理解できます。
例えば、交通事故現場では救急処置だけでなく、二次災害防止、交通規制、現場保全など、様々な要素を同時に考慮しなければなりません。他業務の経験があることで、こうした複合的な現場での判断力が格段に向上します。
メリット3:組織からの信頼とサポート
入庁後取得の場合、組織から派遣される形で養成所に通うため、同僚や上司からの理解とサポートが得られやすくなります。
「頑張って勉強して、みんなのために技術を身につけてこい」という温かい支援の中で学習できることは、精神的にも大きな支えになります。
メリット4:経済的負担の軽減
入庁後取得の場合、養成所の費用は基本的に組織が負担します。また、研修期間中も給与が支給されるため、経済的な心配をすることなく学習に専念できます。
デメリット1:取得までの時間の長さ
最大のデメリットは、資格取得までに最短でも5年程度かかることです。「早く救急救命士として活躍したい」という強い希望がある場合、この待ち時間は非常に長く感じられるでしょう。
入庁後取得者のKさんは、「同期が先に資格を取得していく中で、焦りを感じることがあった」と振り返っています。
デメリット2:競争の激しさ
多くの消防本部では、救急救命士養成所への派遣は選抜制です。筆記試験、勤務評定など厳しい選考をクリアしなければ、研修に参加することすらできません。
希望者全員が行けるわけではないため、「絶対に救急救命士になりたい」という人にとっては、不確実性の高いルートと言えるでしょう。
デメリット3:年齢的な制約
入庁後取得の場合、資格取得時の年齢が30歳〜40歳になることが一般的です。医療技術の習得や体力的な面で、若い時期に取得する方が有利という面もあります。
⚪︎現場で感じる両者の違い

・技術面での違い
入庁前取得者は理論的な知識が豊富で、最新の医学知識を持っていることが多いです。一方、入庁後取得者は実践的な応用力に長けており、困難な現場でも柔軟に対応できる傾向があります。
・組織内での位置づけ
入庁前取得者は「専門家」として期待される反面、「救急以外もできるのか」という目で見られることがあります。入庁後取得者は「チームの中の救急救命士」として自然に受け入れられる傾向があります。
⚪︎あなたにとって、どっちが良い?

・入庁前取得を選ぶべき人
以下のような方には入庁前取得をお勧めします。
強い専門志向がある人
「絶対に救急医療に携わりたい」という明確な目標がある方。医療への情熱が学習の原動力になります。
学習能力に自信がある人
濃密な医学的内容を短期間で習得する必要があるため、効率的な学習ができる方に向いています。
経済的余裕がある人
学校の費用と生活費を賄える経済基盤がある方。奨学金制度もありますが、返済計画も含めて検討が必要です。
・入庁後取得を選ぶべき人
以下のような方には入庁後取得をお勧めします。
消防業務全般に興味がある人
消火、救助、予防などすべての業務を経験してから専門性を高めたい方。幅広い視野を持った救急救命士になりたい方。
組織の中で着実にキャリアを築きたい人
同期と同じペースでキャリアを形成し、将来的には管理職も視野に入れている方。
経済的負担を避けたい人
学費の心配をせずに資格取得したい方。家庭を持つ予定がある方にも安心です。
じっくり学習したい人
現場経験を積みながら段階的に専門知識を身につけたい方。
⚪︎まとめ:あなたにとっての最適解を見つける
・正解は一つではない
この記事を通じてお伝えしたいのは、「どちらが正しい」という答えはないということです。あなたの価値観、経済状況、キャリア目標によって最適解は変わります。
・重要な判断基準
選択の際に考慮すべき主な要素
1. 経済状況:学校の費用を負担できるか
2. 時間軸:いつまでに救急救命士になりたいか
3. 専門志向:救急医療への情熱の強さ
4. キャリア目標:将来どのような消防士になりたいか
5. 学習スタイル:理論先行型か経験先行型か
・最終的なアドバイス
どちらのルートを選んでも、重要なのは「継続的な学習」と「現場での実践」です。資格取得はゴールではなく、スタートラインです。
入庁前取得者は現場経験を積極的に積み、入庁後取得者は最新の医学知識の習得を怠らない。この姿勢があれば、どちらのルートでも優秀な救急救命士になることができます。
また、近年は救急救命士の活動範囲が拡大しており、消防以外でも活躍の場が広がっています。病院、ドクターヘリ、海外での国際協力など、様々な可能性があることも付け加えておきます。
⚪︎最後に
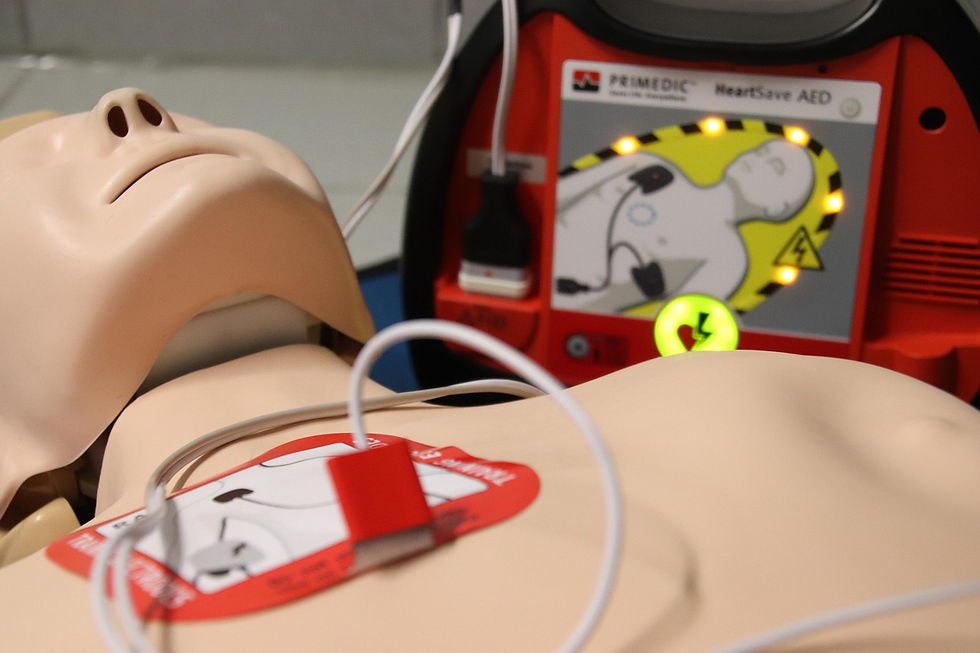
救急救命士は、文字通り「命を救う」専門職です。どのルートで資格を取得したとしても、その責任の重さは変わりません。
あなたが選ぶ道が、将来多くの命を救うことにつながることを期待しています。この記事が、そのための第一歩を踏み出すお手伝いになれば幸いです。
あなたの救急救命士への道のりを、心から応援しています。
これから消防士を目指す人には「FFA」がおすすめです。FFAは、消防士を目指す人に向けたオンラインスクールで、東京消防庁OB、地方消防OBが在籍し消防の採用試験合格に向けて指導しています。
試験対策だけでなく、リアルな現場の話や、講師の実体験も聞けるので、救急救命士になりたい人だけでなく幅広い知識を知りたい人におすすめです。
公式LINEで無料相談も実施しています。ご連絡お待ちしています。

コメント